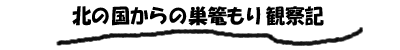
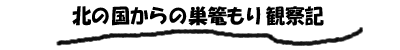 |
|
backnumber
|
|
|
|
 |
《エントランスドアは最後の砦》 勉強のため4年間日本を離れ、久しぶりに里帰りした時に味わったあの恐怖感は今も忘れる事なく思い出されます。懐かしい筈のわが 家が、怖くて一人でいる事が出来ませんでした。 春の陽射しが暖かく 通りすぎる様に、家も、庭も、一体となって開放されている日本の家。 今にも誰かがぬっと家の中に入ってくる様な気配を、そよ風の中にも 感じてしまうのです。 しっかりと塀も門もあるのですが、窓という窓は全部気持ち良く開け放たれ 其の上、ベランダのはきだし窓は大男でも平気に入れるだけの広さで、 のんびりと春の風を呼んでいるのです。近所の子供の声がすぐ横に 響いて聞こえます。 自分と他人との区別を認識していない無防備な家、 鍵の持つ意味を理解していない生活。 こちらの住宅地ではよほどの家で無い限り、塀を四方に廻しゲートを つけることは無く、芝生にかこまれた開放的な庭がはればれとつながります。 しかし、そこには暗黙の契約があるのです。歩道より先は個人のテリトリーで 立ち入り禁止、それ以上入る事は侵入罪で訴えられる事を覚悟する事に繋がります。 そして家の玄関ドアはもちろん、ドアというドアには必ず鍵があります。 ドアだけではなく家中の窓もしっかりと錠が掛かっているのです。 鍵を掛ける生活、鍵を掛けると云う仕草は、ドアを閉めれば個人の生活で 他人又は社会と言い替えても良いのですが、他を自分の許可無しには 容易に侵入させない最後の砦に鍵を掛けていると云う、思考の現われなのです。 自分と他人と云う関係を体験した後で、自分を守る砦の意識の薄い日本の住まいは、カルチャーショックを超えた恐怖の体験だったのです。 これはかれこれ20年前の話。この様な視点から住まいのあり方をみるのも興味深いものです。 |
 |
|
 |
《玄関ホールと風除室》 玄関を入ればそこは自分の世界と云う思考から、家族の生活の場は出来るだけオープンに作られます。 自分の家に連れて来る他人は家族同等の人達ですから、ドアをぬけたら 一気に家庭の雰囲気に飛び込むのです。 しかしここ北の国では冬期に備えよく 使われている住まいの形態があります。広さには家の規模で差がありますが、 室内に入る前の小さな空間がもうひとつのドアで仕切られて作られます。 外の冷たい空気をここで止め、暖房費が嵩まないようにとの工夫です。 風除室と呼ばれるこの空間は、その内側にもうひとつドアがありますから よくガラス入りのドアがつけられます。 ガラス越しにほのかに洩れてくる 家の明りはレースのカーテンの優しさと相まってその家の住人の雰囲気が たそがれ時に伝わって来ます。 風除室が無い場合も、やはりホールと云われる空間があり、外と内とを 仕切りそこから居間や食堂へと導いてくれます。 ホールと風除室の両方を備えた家もあります。 予算に応じてその形状は 様々ですが、冬期の暖房費を節約すると云う機能以上に、住まいは 個人の空間である事を主張しているようです。 玄関のドアを入る事は、敷居を超えたと言う諺にもある様に、あるハードルを 超えて何かをし遂げて前進することを意味します。自分と他の認識が明確で、それを超える事の持つ意味の大切さを 玄関は意志表示しているようです。 Back |
 |
《VR、Virtual reality : vr001》 町を運転している時、またのんびりと散歩している時、 私にはとても楽しい 趣味があります。それはVRの世界に遊ぶことです。何も高価な仕掛けはいり ません。ただ私のイマジネーションの世界に入るだけでいいのです。 この家はこの週末にふと通りかかった家ですが、なにかが私を招待してくれました。 家の気とでもいうものが呼んでいたのです。今年は雪が少なく、気温も穏やかで 過ごしやすいですが、やはり北の国ですから雪とのつきあいは5月始めまで続きます。 ともすると滞り、黒く固まってしまう雪を、この家の人は毎日きちんと始末して、 テュレルと呼ばれる尖塔のあるこの家を愛着を持って大切にしているようです。 それが外壁はごつごつしていますがやさしさを感じさせるのでしょう。 アールのついたこの木の扉を開けると、少し天井の低い薄あかりの入る風除室が 私を招きいれてくれます。 正面にはやはりアーチの入り口がありますがドアはついていません。 このアーチをくぐると玄関ホールになっています。そこの床は石が敷かれています。 外と同じ色合いの石です。壁は腰壁は杉いやオークの浮彫り型のパネルで上半分は しっくい仕上げです。右側に同じ様にオークのよく磨きこまれたてすり子のついた 階段があります。登りきった所にちいさな窓があり外が見えて夕方家の者が帰って 来る姿をみつける事ができます。 玄関上の階段ホールの壁には、下からウオールワッシャーの淡い光が、石の凹凸を 浮かびあがらせています。その前に丈の長いドライフラワーの麦の穂束が、やはり丈の ある厚いクリスタルのつぼに無造作に投げ入れてあります。建てられた当時はこの 小さい窓だけでしたがこの家人は反対側にもうひとつ新しく窓を足しました。方角 からしてきっと朝の光も欲しかったのでしょう。あまりの情熱に少し大きすぎる 窓にしてしまいました.......... VR遊びも今日はここまで。また遊びに来ますね。 ありがとう....... . Back |
 |
|
 |
玄関はそこに住む人の顔? どうして日本の家はドアを外開きにするのですか? 法規では規定されていません。カナダではドアは内開きです。理由は万一の場合、力でドアを開かれないように内側に丁番が隠れ、また、チェーンの設置、手で閉め帰すためです。 ここは雪が多く、また雨も降ります。期間の長い日本とは多少の差はありますが、雨が降っていれば玄関が濡れます。 ストームドアというメタルのドアを外開きにつける事はありますが、それは内側の木のドアを保護するためです。こちらではドアを開いても身動きの出来る空間をとるからです。 家に戻ってきて、ほっと一息つける我が家の空気がそこには待っているのです。昔の和風住宅を思い出して下さい。開き戸をあけて玄関に入れば、家の外と内を分ける心の動きに対応してくれる空間がありました。いつの頃から、いわゆる文化住宅という玄関は、靴を脱ぐだけの仕草の場所となっています。この様な所に内側に開けるドアをつける余裕はありません。 玄関をもう一度見直しましょう。そうすれば色々な生活行動がそこに蘇ります。 |
 |
|
 |
|
 |
|
モントリオールの青空族 町なかの住宅形態は集合住宅が多くこちらは地下は居住空間ですから車は後輩として 扱われて青空駐車が普通です。戦後に建てられたアパートは、地下にパーキングが設 けられる様になりましたが、とても全部の車をいれる事は出来ませんから、やはり多くが 青空族です。駐車違反にならない為には、区役所に年20ドル程払ってスティッカーを貰い後ろの窓に貼っておき ます。 お墨付の無いよそ者の車は罰金を取られるのです。 住宅地に行きますと車庫の付いた家がほとんどです。それでも2台分のガレージ のついた家はまれで、ガレージ前のカーポートにもう1台か2台青空族がいます。そ のガレージをよく観察するとどうも車は肩身狭く同居させて貰っている様で、よほど天 候の悪い日以外は青空族に格下げです。 どうして?ガレージはその家のあるじ の城なのです。きこりの先祖の血がさわぐのでしょうか、こちらはDIYがもう 日常茶飯事ですから、工作室に占領されつつあり、それも本職顔負けの立派な工作台なのです。壁には工具が誇らしげに展示されています。その脇に芝かり機、雪かき機、 芝の水まき機、そして落ち葉吹き飛ばし機と色々な道具があり、今流行の4x4はもうは み出してしまいます。 こちらのあるじ殿は余暇を見つけてこの4x4を繰り出し、ホー ムセンターに出かけていろいろと新しい物を見つけて来て、家をいじるのが趣味なので す。 日本は如何がですか?ガレージを家に組み入れる事は土地の制限もあり難しいかも知れませんが、家のあ るじ殿の城をどこかに設ける事は、住まいを豊かにする意味で書斎より優先させた方が いいかも知れません。同じ青空族でもこちらの青空族は家のあるじ殿の喜ぶ姿を見て納得している様です。 Back |
 |
 |
 |
|
キッチンが先かバスルームが先か? 家を直す時はこのどちらかが先になります。そして最後に窓を直します。外を新しく 直せばおかみの目にすぐ留まり不動産税が上がるからからです。 家の価値が上がれば 高く転売出来ますが、税金もしっかり上がる訳です。 ですから内密に改造できるところ から始めます。 今流行のバスルームはスパの様になって来ています。特にベビーブーマーと言われ る世代がいよいよ子育てが終わり、家をどうするか考える時期にさしかかっています。改造の際にバスルームをスパの様に改善したり、キッチンをグルメキッチンにしたり、お 金をかけ、自分の家で豪華なひとときが過ごせる様に直します。 一頃はジャクジが流行りましたが今はシャワーのジェット型が人気があります。のん びりとジャクジに浸っているよりもデラックスシャワーが生活様式に合っているので しょう。 キッチンもホームセンターにいくと好みのシステムキチンをセットで簡単に購入で きます。アパートを引っ越す時、キッチンセットも冷蔵庫やレンジと同じく持ち歩く人 もいて、完全に家具として理解されています。 このようにこちらの家は生活サイクル に合わせてごく気軽に衣替え出来るようサポートシステムが完備していますから、ホー ムセンターに行けば材料はすぐ入手出来ます。家を購入した時から居心地のよいスペー スを常に心がけて手入れをする、これがこちらのメンテです。言ってみればメンテが 趣味の人種が住んでいるので見て気持ちの良い家が多いのでしょう。そしてそれが既 存住宅の質を上げている訳です。 キッチン、バスルームの改造の他には幅木、ドア、 ドア取っ手、照明器具、クローゼット又は玄関ドア等にお金をつぎ込ます。一味違う我が家を気軽に創り出すセミナーが人気を呼ぶのは、こういう気軽な対処の仕方を心 得ているからでしょう 。 |
||
 |
 |
 |
|
モントリオールの東地区に行くと表通りに添って限りなく家が繋がっています。 この町は南の河沿いから水道の普及につれて東へ町が広がって行ったからです。 土地の風が北西から吹いて来る為、この町の一般労働者のアパートは南東に作られ、お金持ちのお屋敷は北西の山の手に静かなたたずまいを見せています。 一般庶民のアパートはデュプレックス、トリプレックスとか恐竜の名前みたいですが、 2ー3世帯住宅が多く、場所により6世帯も詰め込んだ3階建てもあります。勿論これ らは木造建築で100年経っているアパートもめずらしくありません。 この町が大 きくなったのは20世紀初期ですが、その頃の税は大通りに面している家の幅で決めら れていましたから、大家さんの税金対策と、アパートの幅は多くが7メートル程で収められています。 一階のアパートはそのまま家に入る事が出来ますから問題無いのですが、2階、3階のアパートは階段が必要です。屋内階段にすれば良いのですが、家賃は 居住面積で決められていましたから、お金にならない無駄な階段はなるべく屋外に付け られました。 その為、邪魔だけれども無視出来ないものとして、この階段と義理のおかあ さんはよく話しの引き合いに出ます。 なるべく家の外に出しておきたい物と言う意味です! 狭いスペースに取り付けられた為、必要上かなり急な螺旋階段になりましたが、 カーブの優しいこの階段、おおくは鉄製ですが、フレンチ階段と呼んで大切にしてい ます。絵葉書でご覧になった方もいらっしゃるでしょう。 夏の夕涼みにモルソン ビールをラッパのみしながらこの階段に腰掛けて、隣人や通りすがりの人とおしゃべり をするのがひとつの絵になっています。ところでこちらでマザーインローと言って 煙たがられているのは奥様のお母さんなのですよ! |
||
 |
||
|
セントローレンス河から北へ向かって南北へ番地は大きくなり、その左側が偶数で、右側 が奇数になっています。又東西は島中央を南北に通るセントローレンス通りと境 に、東と西に各々番地が大きくなり、河側が偶数で、山側が奇数になっています。 家を探して訪ねる時は、このルールをしっかりと頭の中に入れて、番地を確 認してから出かけなければ大変な事になります。こちらは家の前には表札はあり ません。番地がついているだけですから左右良くみて探して下さい!同 番地に何軒もある日本と事なり、個人が単位になっている事を教えています。 そして、番地はそれぞれその家の住人の雰囲気の出ているレタリングのナンバーがドアの近くに ついています。色々なのがありひとつの飾りになっているのでしょう。ライ トや郵便受けと共に玄関の大切な仕掛け人です。 |

Summer kitchen:男子厨房に入るべし 100年前位に建てられた家には勿論強制換気扇は付いていませんでした。 ここの冬はマイナス2ー30度が珍しくないですが、夏もプラス30度まで気温が上ります。 そこで、その頃の家はキッチンの延長にサマーキッチンと呼ばれる半囲いの部屋がバックヤードに面して作られました。 ここで収穫したてのコーンを茹でたり、焼き肉をしたりして屋内に料理の熱気を取り込まない様にし、夕方家族揃ってここで簡単に食事を済ませました。 住形態が都会化した今でもこれが現代のバーベキュー文化のオリジンで、男の仕事なのですバーベキューは以前としてあるじ殿のテリトリーですから、庭に本格的に石や煉瓦積みのファイヤープレースを造る人や、大がかりなガスバーベキューセットを用意して自分で焼いて食べさせる事に生きがいを感じている人は珍しくありません。 そこまでお金を掛け無くても、キッチンで男子が料理する事は食後の皿洗いや週末の買い物をするのと同様に当り前の事です。 広い家にはダイニングルームがまた別にありますが、一般住宅は通常キッチンには食事用のテーブルをおくスペースがあり、家族が食事の間だけでなく食事の前も後も一緒に過ごせる場所です。 例えば子供が宿題をしたり母親が手紙を書いたり、父親が請求書の山に頭を抱え込んだりとよくこちらのテレビドラマに見られる様な光景が繰り広げられます。 ですから男女の区別と料理は無縁です。 鉄人シェフがこちらでも高い視聴率を挙げているのですから見せるキッチンとしてその在り方も変わって行くでしょう。 グルメキッチンと言われるハイテクを駆使したキッチンは単に料理を作る為のみで無く、エンターテイメントとしての魅力を発揮出来る要素を合わせ持たなければ今の購買層には相手にされない様です。 |
|
Sea Gulls :かもめのジョナタン フランスで青春を楽しんでいた頃、『鴎のジョナタン』と言う映画が流行りました。私は映画より前に本を買って読んでいましたから、到底このジョナタンは具象化出来ないと信じて映画は見ませんでした。この本は今でも私の大好きな本のひとつです。ぜひ貴方も読んで下さい。 今日はモントリオールのジョナタンの話しです。 通常は11月の声を聞くと何時の間にか姿を消すジョナタン達は4月の初旬に又戻って来ますが、今年は1ヵ月早くもう空を悠々と舞っています。 これはセントローレンス河の氷が溶けるのに合わせて美味しい魚を求めて来るのか、我々が冬眠から覚めて穴蔵から抜け出し、歩道のカフェテラスに座るのに合わせて戻って来るのか、科学的研究が待たれる事柄です。 ジョナタン達は高い空に舞い上がり命をかけて魚を捕る代わりにもっと簡単な方法を発見しました。フレンチフライやハンバーグは魚より美味しいし、待って居るだけでどこのパーキング場でもカフェテラスでも簡単に食事が出来るのです。人間は生きる為よりも快楽の為に食事をし、いつも残すので神様がジョナタン達を差し向けたのかも知れません。 神様に追加の仕事を言いつけられた者は他にもいます。りす、あなぐま、スカンク、からす、皆一生懸命掃除しています。 公園やパーキング場を掃除してくれる間は可愛いのですが、一歩自分の庭となると話は深刻になります。野菜や花の芽や実を食べ、うっかり優しい顔をして餌などをやると本気で居着いて残業に励みあげくは外壁のちょっとした隙間を突ついたり噛ったりして泊り込んでしまいます。ですから子供達はこれらに餌をやる事は悪い事だと教えられて育ちます。 貴方はりすの巣を観た事ありますか?
|
|
軸組工法と枠組工法 従来の日本家屋の建て方は「軸組工法」。柱や梁などの「軸」を直角に「組」む事で強度を持たせ、建物の根本とします。 「大黒柱」という言葉がある通り、垂直な柱が家の屋台骨を支えているのです。 一方、カナダの家の建て方は「枠組工法」です。木で額縁の様に、「枠」をつくり合板を貼り合わせた後レンガや石を貼ったりして、 強い「外枠」をつくります。柱でなく、壁で家全体を支えるのです。 日本の「軸組工法」の場合、柱の位置によって、間取りが決まります。直角に組まれた軸に合わせるので、部屋は四角四面になります。 画一的とも言えますが、柱や梁がしっかりしているおかげで、「ふすま」を取り外して、大広間にするという芸当もできます。 カナダの「枠組工法」の場合は、外壁がしっかりしているので、家の中の壁を比較的自由に設計することができます。 直角だけでなく、120度の壁や曲面の壁も可能です。 枠組工法の一つである2×4(ツー・バイ・フォー)方式の注文住宅を作る場合、直角にとらわれずに、 もっと自由に発想してもいいのではないかと思います。
|
|
眼に見えない廊下と家具の役割 住空間は大きく分けて3つの使われ方があります。「人が生活する空間」、 「人が移動する空間」、そして「物を仕舞っておく空間」です。この3種類の空間 を組み合わせて家族生活に最適な住まいをつくります。 カナダの通常の住宅は、玄関から直接食堂や居間に入る間取りの家が大半を占め ます。つまりいきなり「生活空間」なのです。かと言って、食堂や居間に人の「移 動空間」がないわけではありません。はっきり仕切られていないだけです。 「移動空間」も「生活空間」のなかに取り込まれているため、部屋はより広く、開 放的になります。外からの光も等しく行き渡るから、明るくなります。 壁に囲まれた廊下で、人の動線(歩く道)を強引に確保するのではありません。大 小のソファやテーブル等を効果的に配置することで、さりげなく用意するのです。 動線の周りに、さまざまな形や色をした家具の組み合わせることにより、おしゃべ りをする場所、食事をする場所、または一人で読書をするコーナーをつくりだしま す。オープンスペースのなかで、家族が同時にそれぞれ好きなことができるように 工夫してあります。 近くにいるけれど気にならないように、個と家族が調和した空間を、家具のアレ ンジと眼に見えない廊下でつくるのです。
|